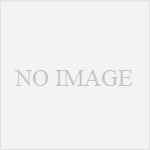
imageJのscaleの単位を変更する
imageJで便利な機能としてmeasureがあります。 たとえば細胞の長さを測ることもできますし、面積や重心、さらには輝度まで測れます。 どのようなものが測れるかはメニューのAnalyse>Set Measurements..から選べます。 こちらに関してはまた時間があるときに詳しく説明しましょう。 今回はimageJのscaleの調節についてですデフォルトのまま使用をするとピクセル数で長さなどが出てしまいます。 それをメートルやインチに設定しなおす方法。つまり単位の設定、変更です。